第三章、映画の内容
身体を通しての心(精神)
映画がその表現のために使用する材料は、物質的対象と自然の出来事のみです。
その中でも人間の顔と身体の動きを手段にした、精神(思考や感情)の表現は、最も直接的で分かりやすいものです。
しかし、日常生活において人間のジェスチャーを意識的に見ることがないため、映画俳優の不自然なほど誇張された動作に気付きません。
日常の自然な動作(自然の演技)は、曖昧で個性的で謎めいていています。
人々(文明人)は、多くの場合ジェスチャーを控え単調であり、その精神状態を示すものがほとんど見えないこともあります。
笑っているように見える泣き顔や、気難しそうな微笑みなど、日常の表現は明確な意味を伝えていません。
均質なメッセージを与えず、解釈が難しいいため、シュチュエーション(状況)の一部として、表情や動作の意味を理解するのです。
文明化された人間関係においては、個人的欲望や思考や感情の表現を抑制することが、社会人の基本としてあるため、動物や子供や原始人に見られるような率直で明白な精神の表現が失われています。
例えば、母親は子供の自然な動作を、社会性という理念によって体系的に潰していきます。
「まっすぐ歩きなさい!」「大人しく(大人らしく)座っていなさい!」。
特に現代人は、多様な動機、複雑で可塑的な思考、衝動と抑圧の衝突など、多種多様な心の動きが全体として統合されないまま、表情やジェスチャーにあらわれるため、より不明確なものとなっています。
しかし、芸術作品では、すべてが明確でなければなりません。
不明確なものも明確のための不明確でなければなりません。
優れた映画俳優とは、「純粋な」表情や演技を作り出せる者です。
日常の表現では不明確が自然であるのであれば、映画の「純粋な」表現は、不自然に見えるはずですが、そうはなりません。
人々(観客)は一見したことの意味を把握するだけで満足するのが普通であり、注意深く観察し比較するような知覚の習慣を持っていません。
それでも観客は、実生活では不完全に感得され、ほのめかされ、込み入った、不明確な事柄を、映画の芸術的表現は、描写対象を説明し、洗練し、明確にすることであることに気付いています。
例えば、恋愛場面のように過度な誇張的(不自然)な演技であっても、自然の模倣ではなく芸術であると理解し受容します。
しかし、演技のスタイル化は、制限内に止める必要があります。
芸術家が自分の芸術の媒体の条件に服従するのは適切なことですが、自然に不忠実にならないようにすることも必要です。
優れた俳優や監督は、できるだけ「演技」を少なくすることで、最高の効果が得られることを示しています。
劇場の条件として誇張した演技を為す舞台俳優とは異なり、映画俳優は、その存在と些細なジェスチャーによって大きな効果を上げます。
ロシア映画においては、俳優は演技を制限され、適切なコンテクスト内に配置されたひとつのプロパティとして機能する存在となります。
よく構成された脚本というコンテクストによって、行動しない俳優の存在とわずかなジェスチャーから、彼の精神状態と周囲の事件についての、明確な意味と説明を瞬間的に与えるのです。
このように映画が、フォトジェニックな説明とカメラの技巧を介して意味を表現することにより、演技の貢献を減らすスタイルを採用する場合、俳優は最終的にたくさんある中の一つの「小道具」になります。
ロシア映画のように、適切な前後関係の内に配置された素人が効果的になるのです。
訓練されたプロの俳優は、演技が必要な場合にのみ必要とされます。
演技が必要である劇場(舞台)の俳優と異なり、映画においては、偶然その映画に合ったリアルな型を持つ者に、キャスティングの機会が生じます。
映画において精神(心)の状態を表現する手段は「演技」だけではないのです。
もし、「演技」の努力に表現が依存するなら、身体の表現は野暮な冴えないものとなり、観客に説明は出来ても感動させることはできません。
サイレント映画は、舞台俳優の身体表現の技巧を失った、ただの「無言劇」なのではないのです。
映画の俳優は、映画内の他の要素(無生物や物語など)と相互協力的に表現を為すため、その演技の比重は軽くなり、おおげさな身振りを必要としなくなります。
映画の主人公の「悲しみ」は、俳優による悲しみの迫真の演技が生じさせるのではなく、その悲しみの事件にいたる前後の物語(上手く構成されたプロット)の重みが生じさせます。
「真剣」は、急に止まるチューインガムを噛む口元によって、「動揺」は、ティーカップを持つ手が震えることによって、表現されます。
タバコの吸い殻の山は、俳優の「苛立ち」の演技と同じような効果を持ち、割れた窓ガラスは、俳優の「絶望」の演技と同じような効果を持ちます。
意味とインベンション
無声映画は言語の役割が小さすぎて、何のアイデア(ideas)も伝えられないとよく言われます。
そのアイデアが抽象的思考を意味する場合であれば、その通りでしょう。
しかし、言語を中心とする文学であっても、多くの場合、具体的な出来事の描写であり、それが抽象的な省察に劣るという訳ではありません。
この点では、文学と映画の間に本質的な違いはなく、描写のために文学は言語を使い、映画は写真を使います。
どちらのメディアであっても、中心となるアイデアは、抽象的ではなく具体的な出来事によって、あらわされます。
映画はその写真表現のインベンション(創意、発明)によって、深い意味の表現を可能にすることは、多くの傑作によって証明されています。
映画におけるインベンションは、時に抽象的アイデアを写真によって表現し、時に具体的事実の印象的な描写のための巧妙な工夫として利用されます。
チャップリンの「黄金狂時代」には忘れがたいかずかずの例が収められている。チャーリーが鍛えた試掘者として、汚れて油を引いた自分の長靴を料理して食べようとするシーンがある。いとも優美に完全なテーブル・マナーで、彼はこの珍らしい料理を切る―上の方を持ちあげると、皿の中に直立したまま釘の打ってある靴底は、肉を取除いた魚の背骨のように残される。彼はちょうどチキンの骨のように釘を注意深く吸う。それからスパゲティのようにフォークで靴紐を巻いて行く。このシーンでの金持と貧乏者のコントラストは、比類のないほど巧みで、斬新的な写実方法で象徴されている。この同じコントラストは、今までになされた通り、貧乏な男のわずかな食事と隣合せに金持ちの男の豪華な料理をフィルムでしめすこともできようが、その結果たるや、抽象的なものから直接取り入れられたのであるから、通俗的であり独創的ではない。したがって訴える力が弱まり、芸術的には価値を失うのである。もし「黄金狂時代」のシーンが、単に鍛えた男が料理した長靴をむさぼり食う様子だけを見せたものならば、それは貧困のグロテスクな戯画にすぎない。このシーンの卓越した力強さは、惨状を描写しながら、この食事のもっとも独創的で目をそば立たせる類似性によって、富のコントラストが同時的に、金持ちの食事にあたえられている事実にある。長靴の残骸=魚の残骸、釘=チキンの骨、靴の紐=スパゲティ。チャップリンは、客観的にこんなに異なっているものの形の類似をしめして、観客の目に痛ましいほど明らかなコントラストを作っている。 この発明の偉大な手腕は、「飢餞対よき生活」という人間の本源的深みのあるテーマを取り上げ、それを真実に映画的な客観的媒体によって絵画的に表現した点である。事物の形の連想から、これ以上純粋に視覚的なものを考え出すことはできない。想像しうる限り一番みじめな食事を、あたかも好みの料理のように、それにふさわしい優美な作法で食べながら、チャップリンはそのような貧困をしめしたばかりでなく、(いわば) 貧困を富の低い段階、よき生活の歪みとしてしめしている。この関係を作り出しながら、 彼は悲惨を二重にみじめに見せている―ちょうど小が大によってますます小さく見え、黒が白と対照されてますます黒く見えるように。(同上)
第四章、完全な映画
サウンド、カラー、3Dと、映画技術の発展は、いずれ完全な自然の機械的模倣を達成します。
新しい映画技術の導入は、「自然の模倣」という非芸術的な要求を可能な限り満たすために、映画芸術家が使用していた形式の多くを破壊します。
新しい技術の導入は、それ自体にある芸術的発展の可能性を提供するため、その得たもののせいで失ったものの大きさに気付きません。
映画技術の発展は、知らぬ間に創造的な芸術を単なる蝋人形に堕とそうとしているのです。
サウンドによって、むしろ映画(イメージの言語)は口を閉ざします。
カラーは、白黒映画にある自然からの独立性(芸術媒体としての固有権)を壊し、映画の芸術的創造的な部分は、「カメラの前」に置かれたものに集中することになります。
3Dによって現実の錯覚が大きくなると、画面上の絵画的要素や、モンタージュなどの構成的技術はうまく機能しなくなり、芸術的可能性は舞台の錯覚のようなものになります。
その時、映画は、もはや独立した芸術と見なすことはできなくなり、むしろ始まりに投げ返されます。
ただ一つの違いは、かつては将来に希望を持っていたのに対し、今は将来に何の可能性も持っていないということです。
この奇妙な発展は、これまで視覚芸術の歴史全般にわたって普及し、また自然への類似を追求する動きのクライマックスを、ある程度まで意味している。忠実な映像を人間に創造させた努力のうちには、物質的対象をあらたに創造することによって人間の支配力の下におく原始的な欲望があるのである。模倣はまた人びとが重要な経験と対抗することを許した。模倣は解放をあたえ、自己と外界の間に一種の相関性を作りだす。と同時に、正確な自然の再製(リプロダクション)は、人間の手によってある自然物に驚くほどよく似ている映像を創り出したというスリルをあたえたのである。それにもかかわらず、多種多様の逆な傾向が-あるものはまったく知覚的であるが-数百年以前に成しとげられた機械的な忠実な模倣を妨害してきた。数少ない例外を除けば、私たちの近代的時代は、この危険なゴールへ接近するのにようやく成功したばかりなのである。 実際上、模写するのみならず、 創作し、解釈し、型どる芸術的な衝動はつねに存在していた。しかしながら美学上の定説は、この種の動きをほとんど認めていないといってもよい。 レオナルド・ダ・ヴィンチのような芸術家でさえも、できる限り自然に忠実・正確であれという主張は、彼が理論を語る時には当り前のことであったし、プラトンが芸術家を攻撃して自然的対象の複写ばかりしていると責めた態度は、一般からはかなり離れていた。(同上)
現代でも、一部の芸術家や一般人の多くが、この自然の再製というドグマを大切にしています。
このドグマを知的に破ろうとする現代の芸術家が強い拒絶を受けるのは、そのためです。
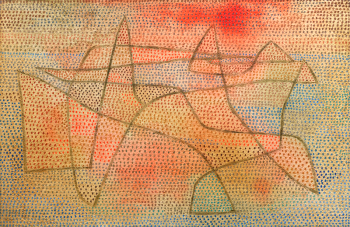
パウル・クレー『島』1932年、ブリヂストン美術館
映画は既存の美術より自然に近いメディアであるため一般人は映画を高く評価し、また、映画製作は経済的に一般大衆に依存するため(興行成績)、大衆の芸術的嗜好がすべてを席巻します。
芸術的に質の高い作品が生じても、映画芸術の根本的敗北を補うものではありません。
完全な映画は、完全な錯覚を求める長年の努力の成就であり、その時、オリジナルとコピーは実質的に区別がつかなくなります。
これにより、モデルとコピーの相違に基づいていたあらゆる創造的構成的可能性が排除され、オリジナルに固有のものだけが芸術に残ります。
「完全な映画」の完成は、悲劇的な破滅に終わるという訳ではありません。
サイレント映画、サウンド映画、カラー映画などの他の映画の形式と共存することが許されれば、むしろそれぞれの映画形式をより強く推し進めることになるからです。
例えば映画の存在によって、舞台がその特徴である劇的台詞の優位性を強調する様に、「完全な映画」の存在は、各映画形式を独自の領域に追いやり純化します。
自然の完全な複製を達成する「完全な映画」と、各々独自の芸術的形式を持つ映画は、そうやって共存しつつ、前者は後者の進歩と見られることになります。
おわり
