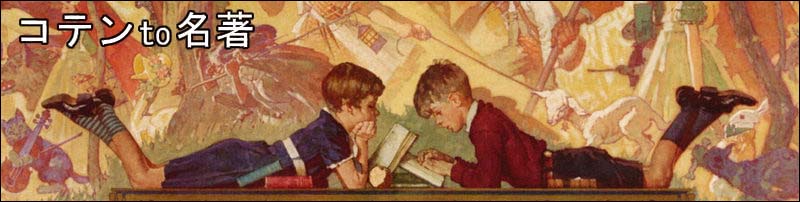死(にまつわること)を思うことの効用は無数にありますが、最も言及されるのは、人生の終わりとしての死です。
人は終わりを意識することによって、今の行動に充実した意味を与えることができます。
そこはかとなく卒業という終わりを意識しているがゆえに、クラスメートとの交流は輝きを増します。
終わり(区切り)を設けない勉強や仕事は、集中力や熱が失われ、中身の薄いものになってしまいます。
例えば、画家は、カンバスのサイズや形を先に決定し、常にその限界を意識しているからこそ、そこに描く線や面に一定の角度や大きさや形をもたせることができます(無限大・不定形のカンバスに何を描いても溶けていきます)。
それと同様、私の描く人生の一筆一筆も、ある程度の枠の限界を意識していないと、そこに意味をもたせにくくなります。
「人生の終わり(死)を意識なんてすれば、むしろ俺の行動の意味は失われる。だって、死んだらすべてが消えるんだから、すべて無意味だろ」と、考える人も多くいますが、彼らは本質的な部分で見誤っています。
人間は欲求にかられて行動する生き物であり、その欲求が充たされれば行動を停止しますが、しばらくすると次の欲求が生じ、また行動を開始します。
画家が全身全霊をかけてこれ以上ないという最高の作品を生み出したと思っても、しばらくすると、その作品を物足りなく感じ、新たな創作欲求によって、ふたたび筆をとります。
前の作品を白の絵の具で塗りつぶして、その上から新しい絵を描き始める画家もよくいます。
それと同様、いかに意味ある八十年の人生を送ったとしても、もし人間の生がもっと長かったとしたら、その人生を自ら捨て、新たな人生に向けての行動に走り出すはずです。
ノーベル賞学者は己の地位を自ら捨て、名も無き冒険家になるかもしれません。
つまり、死んだらすべて消える云々以前に、遅かれ早かれ私は意味ある人生を自ら捨てるのです。
私たちは生存に直接関わる欲求(食や睡眠欲など)を除けば、(欲求充足の)目的を達成するために行動しているのではなく、行動を起動させるために目的を立てているのです。
「人間は死ぬからすべての行動(ひいては行動の総体としての人生)は無意味だ」と言う人々は、この事実が見えていません。
死ぬ死なない関係なく、元から人生は無意味なのです。
意味と無意味は撚り合い、一本の糸のようになっており、人生における無意味とは「自由」の別名、意味とは「運命」の別名です。
無意味(自由)という真っ白なカンバス地があるからこそ、そこに意味(運命)を描き出すことができます。
「(人生の終わりとしての)死を思え」とは、この真っ白なカンバス地を切り出し、ある特定のサイズと形の木枠に貼る作業です。
そのカンバスにどんな意味(運命)を描き出すかは、その人自身にゆだねられています。
おわり