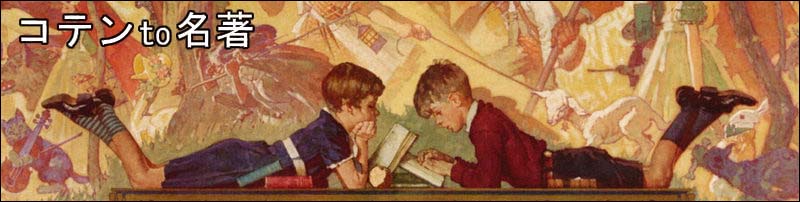死を思うと、強い不安や恐怖に襲われることがあります。
自分の居無い世界のことを考えると、脳がめまいを起したような焦燥感が生じます。
人間は完全な無を考えることができず、常に無は何らかの有に対しての限定的な無です。
ゼロは数の無い状態、空間的な無は物体の無い状態です。
だまし絵のルビン(心理学者)の壺のように、スポットを当てた方(「有」)の反対側を思考したものが「無」です。

無を思考する際に隠れた前提になっているものが、認識する人間(私という主体)です。
壺と顔の間の境界線を引くように、片方を「有」もう片方を「無」と、自ら分割し、それを認識する主体(観る私)なしには、無は成立しないのです。
ですから、「物体の無い無(空虚)の世界」や「私が居なくとも回る地球」は容易に想像することができますが、「私(認識主体そのもの)がない無の世界(つまり完全な無)」は、決して想像することができず、思考が空転してしまいます。
それは、「円形の四角形」や「イチであるゼロ」などの考えることのできないものを、無理に考え続けるようなものです。
私たちは多くの場合、その際に生じる思考のめまい(混乱状態)を、死に対する不安と取り違え、恐怖しているのです。
また、人は死ぬ瞬間、意識を失うため、死を体験することができません。
つまり死そのものは、思考によって考えることも出来なければ、感覚によって体験することも出来ないものなのです。
ただ、周囲の人々が亡くなる姿を見て間接的かつ外的に死を想像し、自分が睡眠する体験を通して間接的かつ内的に死を想像します。
私にとって死は、永遠に間接的な想像でありつづけるのです。
死そのものを思うことは、『不思議の国のアリス』のようなナンセンスの戯れに耽るのに等しく(いわば「円形の四角形」を空想し遊ぶ世界)、楽しむのはいいとしても、望みもしない不安や恐怖をもつのは無益です。
「死そのもの」ではなく、「死にまつわること」を考えることが有益であるのは、過去の多くの賢人たちが教えてくれています。
つまり、「死(にまつわること)を思え」、しかし、「死(そのもの)を思うなかれ」ということです。
死(そのもの)に対する不毛な思考を、死(にまつわること)に対する有益な思考へと向け変えねばなりません。
おわり