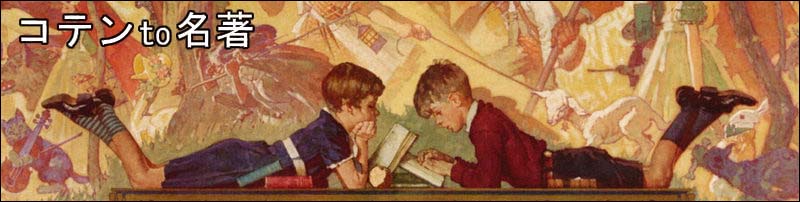人間は常に何かを志向しています(熟睡している時以外は)。
志向なしには何も認識することができません。
その人間の志向性を、あるドイツの哲学者は「気遣い」と呼びます。
また、何かを志向する時、同時に他の何かを志向することはできません。
過去ばかり気遣う人は未来と現在を気遣うことができず、現在ばかり気遣う人は未来と過去を気遣うことができません。
また、気遣いには方向だけでなく、程度(強度)もあります。
気遣いの方向と程度が適切であれば、その人の人生は過ごしやすいものになり、不適切であれば、困難な人生になります。
例えば、会話をする時、相手ではなく自分ばかりを気遣ったり、相手を気遣うにしても過度に気遣いすぎたりすれば、上手く喋れなかったり伝わらなかったりします。
気遣いの悪い典型例が心気症(病気不安症)と呼ばれるものです。
気遣い(志向)が常に自分の身体に向けられ、なおかつ過度な程度に向けられている状態であり、些細な身体の徴候をすべて大病に結び付けます。
思考のイメージは、それに沿った環境を生み出し、イメージを現実化する傾向があります。
例えば、モテない自分をイメージする人は異性に対する消極的な態度を生じさせ結果として恋人を得る確率が下がり、モテる自分をイメージする人は異性に対する積極的な態度を生じさせ結果として恋人を得る確率が上がります。
病気をイメージする心気症の人は、自ら病気になりやすいような環境を作り出し、本当に病気になり、身体症状が増加し、さらに不安の兆候が増し、その悪循環の輪がどんどん深くなっていきます。
精神的に健全な人は、適当(適切の意)な時に自分の身体を気遣い(志向し)、適当な程度(強度)で関わっているため、些細な兆候は無視し、重要だと思われる場合のみ病院へ行きます。
精神の健康な人は、下のスヌーピーのように、常に適切な気遣いの方向をわきまえているのです。

「そんなことは分かっている。でもできないんだ。いつも私は嫌いな人のことを考えたり、病気になることを恐れたり、過去の過ちを思い出したり、人の不幸を探し回ったり、ネガティブなものへの気遣い(志向)を止められないんだ!」と言う人も多くいるでしょう。
しかし、好きな人のこと(ポジティブ)より嫌いな人のこと(ネガティブ)を考えてしまうのは、単なる習慣的な志向であり、自分の望んでいる志向ではありません。
ただ習慣的に左利きになってしまったから、左利きが不便でも、右利きに直すのが面倒なので(別に望んではいないが)左利きのままで居る、のと同じです。
「思考が行動になり、行動が習慣になり、習慣が人格になり、人格が人生(運命)になる」と或るアメリカの哲学者が述べるように、思考と行動の積み重ねで習慣化した気遣いを、別の習慣へと矯正すればよいだけなのです(左利きを右利きにするように)。
嫌いな人のことを考えそうになったら好きな人のことを考える、というトライアルを何度も繰り返しているうちに、いずれ嫌いな人のことを考えることに違和感を覚え、好きな人のことを考えることが習慣となり、次いでそれは性格となり、次いでそれは人生となります。
ポジティブな人生(運命)は、自らの努力で作るものです。
おわり
※勿論、適切な志向は状況によって変わるものであり、習慣化とは相反するもののように思われるかもしれません。しかし、状況の変化には期間の長さと可能性としての範囲があり、長期的あるいは広範に有効な適切な志向というものも多くあるため、そういうものは習慣化した方が良い、と言っています。