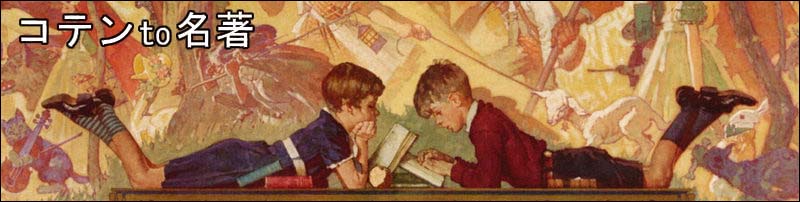「考えすぎるな」という忠告を、よく耳にします。
様々な文脈で用いられるので、その意味も様々です。
ブラック企業の先輩が目覚めそうになった後輩に言う「考えすぎるな」は、それ以上の思考の停止の指示であり、スポーツの監督が述べる「考えすぎるな」は、理論(仮説構築)に偏りすぎた選手に実践(実験)を促すものです。
「考えるな」ではなく「考えすぎるな」であり、問題となっているのは考えることそのものではなく、”すぎる”という部分ですが、すぎている(余計な過剰)部分をはかる物差し(基準)は、上の例のように状況により異なるため、断定できません。
全ての状況に共通するよう、一般的に書き替え、「意味のあることは考え、意味のないことは考えるな」と言えるくらいです。
しかし、その(或る特定の)状況において、何が意味あることで何が意味のない事かを明確にするのは、なかなか難しいことです。
それ(意味あることと無意味なことの基準)が分かっていれば、そもそも「考えすぎるな」などという忠告など受けるまでもなく、考えても意味の無いことは考えないだけだからです。
一般的なだけでは足りず、もっと容易な方法が必要です。
ここで参考になるのが、古代ギリシャのストアの賢人の生き方です。
それは、「自分に制御(コントロール)可能なことは考え、自分に制御(コントロール)不可能なことは考えるな」というような態度です。
例えば、大地震が起こることを考え怯えることは、自分にはコントロール外のことで無意味ですが、大地震に備えいかなる防災体制を整えるかを考えることは、自分のコントロール内のことで意味をもちます。
ストアの賢人にとって「考えすぎ」の”すぎ”の部分は、”コントロール不可能なことを考えること”を指しています。
人に嫌われないか、大きな病気にかからないか、試験に落ちないか、解雇されないか、などという「考えすぎ(自分にとって制御外のことについての考え)」の部分を捨てることです。
そして、思考は自身のコントロール内のことだけに使うのです。
嫌われることではなく尊敬されるような立派な人間に成ることを考え、病気にかかることではなく健康であり続けるための方法を考え、落第や解雇ではなく学力や職能の向上のことを考えるのです。
ストア的な意味(制御内のことは有意味)と無意味(制御外のことは無意味)は、最初に述べた特定の状況における意味と無意味の基準より一般的(万事に共通)なものであるため、この根本的態度によって、特定の状況における無意味な考えも事前にかなりの量を除去することができます。
目の大きなフィルターによって、ある程度、思考を浄化しておくことができるため、「考えすぎるな」などという忠告を受ける頻度も減るでしょう。
特定の状況における意味ある考えと無意味な考えを分別判断することは困難ですが、自分の制御内のことか制御外のことかを判断することは、それに比べれば大分容易です。
おわり