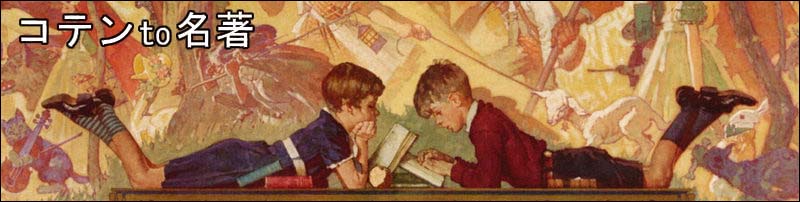第一章、商品の成立
使用価値と交換価値
使用価値とはその名の通り、何らかの物を使用する際の具体的な有用性の価値です。
パンは食べて栄養にするものであり、レコードは音楽を聴いて慰安をえるための物です。
交換価値とは、それが社会的な他者との交換の場(市場)において、どれくらいの価値を持つかという尺度です。
リンゴ1個100円で、マンゴーが1個1000円したとすると、マンゴーはリンゴの10倍の価値を持つことになります。
100g100円のしめじの方が100g8000円の松茸より栄養価が高く美味しく、使用価値では劣らないにしても、交換価値においては八十分の一しかありません。
この交換価値というものは、需要と供給によってある程度決まります。
マグロの大トロは一匹あたりほんの少しの部位しか取れないため、市場に出回る供給量が少なく、かつ人気があり皆が欲しがる(需要が多い)ため交換価値が非常に大きく(値段が高く)なります。
昔は大トロは脂の塊で捨てる部分であったため、その時代においては需要がないため、交換価値としてはゼロです。
労働価値
しかし、需要と供給はある程度の幅で交換価値を変動させるだけです。
いくら豊作でもリンゴ1個5円では商売になりませんし、壊滅的な不作でも松茸一本百万円ではほとんど買い手がつきません。
そこで交換価値(=価格)を決定するための、もっと本質的なものを考える必要があります。
その基本的なものをシンプルに「価値」と名付けます。
交換価値(=市場価格)の基体ともいえる「価値」です。
分かりやすくいえば、需要と供給が一致したとして、その影響を取り去った時の、自然な交換価値あるいは自然な価格が「価値」です。
その「価値」を決定するものは、それを生産(再生産)するために必要な労働量です。
日本の気候でマンゴーを作ることはリンゴを作ることよりも難しく、1個当たりより多くの労働量を必要とするため、価値が高くなります。
仮に日本の労働人口を五千万人として、一人あたり平均一日十時間働いたとして、社会全体の総労働量は一日五億時間です。
その限られた労働量を様々な生産物に費やし配分されているわけですから、必然的にそれぞれの生産物の価値の差が、その生産に必要な労働時間の消費量に合わせて決定されます。
純粋な商品の「価値」の大きさは、イコール、その生産に社会的に必要な労働時間です。
そしてこの価値は需要と供給の動きに連動し、市場の中で自動的に価値の配分を制御する自律的なシステムとして作動します。
仮にリンゴ10個作るのに労働量一時間、マンゴー10個に十時間かかったとすると、等価な交換価値はリンゴ1個100円とするなら、マンゴー1個1000円です。
もし仮に市場価格がリンゴ100円、マンゴー2000円になったとしたら、必然的に果実生産者はより利益の大きくなるマンゴー生産に乗りかえることになり、マンゴーの供給量が増え自動的に価格が下がることになります。
物象化
このような市場システムの中では、むしろ生産者は価値を持った生産物である商品の交換価値を見ながら、自分達の生産を調整することになります。
生産物を作る主人である生産者であるはずの私が、商品という生産物に指導を仰ぐ奴隷となる逆転現象です。
商品の価値というものが、あくまでも人間の社会的な関係性から生じた観念であるにもかかわらず、主人と化した商品は、まるでその価値を物体がもつ自然属性であるかのように振舞いはじめます。
商品という単なる関係性の観念が、自然物のように捉えられることを「物象化」と呼びます。
第二章、貨幣の成立
価格の成立
私たちが市場において商品を交換する時、その使用価値では交換の基準にならないため、その商品価値の基準において交換します。
商品価値は社会的関係性が生み出す抽象的なものであるため目に見えず、そのままでは交換相手にはその価値が分かりません。
そこで必要となるのが「値札(価格)」であり、値札を成立させるために必要なものが「貨幣」です。
貨幣の成立
仮に貨幣のない物々交換の世界で、私が仕立て屋であったとします。
私は服しか作れないため、晩ご飯の魚を得るために猟師さんのもとへ服を持って交換に行きます。
しかし猟師は服はあるから要らない、船を補修するための木材が欲しいといいます。
それで私は木こりのところへ行って服と木材を交換してくれと言うと、服は要らんから酒をくれと言います。
結局、造り酒屋まで行ってようやく服と酒を交換してもらえ、今度は来た順を逆にめぐり交換して、晩の魚にありつけます。
これでは非常に非効率な交換になってしまいますので、皆が共通に必要とするものを「一般的等価物」として交換を行おうということになります。
例えば、誰もが毎日必要な「パン」を交換の軸とした場合、服1着=丸パン5個、魚1匹=丸パン2個、木材一本=丸パン10個、酒1瓶=丸パン3個となったとします。
このような価値表現を「一般的価値形態」といいます。
そうすれば、わざわざ物々交換のはしごなどせずとも、家にある丸パンのストック2個を猟師のところへ持っていけばよいだけです。
しかし、いくら保存の利く乾燥パンでも時間により腐り、大きさを持つため家1軒=丸パン5,000個を求められた時どうしようもなくなります。
だから「一般的等価物」として最適なものとしての条件がいくつかあります。
耐久性があること、分割したり合一したり出来るもの、希少であり価値の比重が高いこと、生活必需品でないこと、などです。
そこで歴史的に最も「一般的等価物」として適切だとして採用されたものが「金(ゴールド)」です。
家1軒を欲しい時でも、腐らないし場所もとらない金の延べ棒一本(1kg)を持って行けばいいだけなので、非常に効率的です。
この貨幣形態において固定化された一般的等価物を「貨幣」とよびます。
貨幣の魔力
この何とでも交換可能な貨幣というものは、まるで何にでも変身し全てに充ちる変幻自在の神のような非常に強力な魔力を持ちます。
ポーカーゲームにおけるワイルドカードのジョーカー(全てのカードとして使える)は、ツーペアをフルハウスにし、スリーカードをフォーカードにする無敵の力を持っています。
マルクスの挙げた例でいうなら、脚の悪い人間も金で三頭立て馬車を買えば誰よりも早く移動できる者となり、醜男も金の力で美女を傍におくことができます。
友情は友情と、愛は愛としか交換できなかったはずが、いつの間にか愛も友情も貨幣の交換物となりさがります。
まさに「Money is everything.(カネはすべて)」なわけです。
物理的限界のある使用価値への限られた欲望は、観念であるがゆえに永久に充たされることのない貨幣への無限の欲望に取って代わられ、人間は疲弊していきます。
人間は単なる観念でしかない商品価値や貨幣を、先天的な属性を持つ自然物のように捉えはじめ(物象化)、やがてそれは偶像幻想的な「物神崇拝(フェティシズム)」にいたり、人間は人間自身の自然的営みから疎外されます。
第三章、資本家と労働者
資本と資本家
通常の経済的営みを図式化すると「商品→貨幣→商品」となります。
仕立て屋である私は服という商品を貨幣に交換(販売)し、今度はその貨幣で生活を維持するために必要なものと交換(購買)します。
けれど、この図式を変えて、貨幣そのものを目的とすることもできます。
「貨幣→商品→貨幣」となり、使用価値として必要だから商品を買うのではなく、売るためだけに商品を買うという行為です。
需要と供給の変動を見ながら、安いときに商品を買って、高いときに売れば、その差額が儲けになります。
土地や株の投機などが典型です。
一見、これによって価値が増殖したように見えますが、この方法は単に他人のお金を自分の懐に入れているだけで、イス取り合戦のように私の儲けは誰かの損失であり、全体で見ると価値は釣り合っており、別に上昇しているわけではありません。
あくまで商品の基本的な「価値」だけに則した「貨幣→商品→貨幣」のサイクルにより、商品に内在する力によって自己増殖する価値を「資本」といい、これを遂行する人を「資本家」とよびます。
(後に述べますが、労働力は価値を増殖させ変動させるため「可変資本」、生産手段は価値移転はしてもトータルの価値に増減がないので「不変資本」とよびます)
この、等価交換であるにもかかわらず価値を増大させる資本という謎を解くことが、資本論の大きな目的のひとつになります。
労働力商品
その謎を解く鍵は、資本家は労働力を商品にすることが出来るということにあります。
「貨幣→労働力商品(労働者)→貨幣」、お金を労働力と交換(雇用)して、労働力によって貨幣に交換する生産物を作るということです。
資本主義社会に生れ落ちる人間は、万物が誰かの所有物である世界にいきなり参入します。
何か生産して生活の糧にしようとして、生産手段を見渡すと、すべて他人のものです。
作物を作るための土地も、種も、水も、馬も、農耕具も、生産手段すべて誰かのもので、それと交換するためには貨幣が要ります。
だから親の貨幣や生産手段を相続しない限り何も持たない人間は、自分の労働力を売るしか方法がない訳です。
資本家とは生産手段をたくさん持ち労働者(労働力商品)を買う人で、労働者とは生産手段を持たないために自分自身を労働力商品として売る人です。
労働力の価値
商品販売の第一の目的はその商品の生産の継続、再生産です。
私が仕立て屋であった場合、服を売って「商品→貨幣→商品」のサイクルを繰り返し、自分の生活を維持することが基本的な目的です。
店やミシンのローン、材料費や私の食費に生活費など、次の洋服を再生産するための費用がまかなえないなら、仕立て屋としてやっていけません。
それと同じように労働力商品の対価(交換に必要な貨幣価値)も、それの再生産可能性が基準になります。
衣・食・住、扶養家族の養育費や職業技能の獲得と維持に要する費用等、労働者(労働力商品)が生存しかつ生産力を維持できる程度に健康であって、繰り返し再生産のサイクルに乗ってくれる程度の対価です。
労働力の価値とは、労働力の再生産費によって決定するということです。
第四章、剰余価値の成立
剰余価値
仮に前項において述べたような労働力の再生産が、一日一万円で可能な国であったとします。
資本家に雇われの身になった仕立て屋の私が作ったスーツの売り上げから、生産手段や販売にかかった費用などすべて差し引いた額を私の要した労働時間で割れば、私の労働が生み出す時間単位の価値が表せます。
それを一時間2,000円とした場合、一日8時間契約なら、16,000円の価値を私は産出します。
しかし、支払われるのは雇用契約書通りの固定給一日あたり一万円です。
これにより「貨幣→労働力商品(労働者)→貨幣」の等価交換のサイクルは、「10,000円→労働力商品(労働者)→16,000円」という自己増殖を生じさせます。
この増殖した分の価値を「剰余価値」といいます。
労働時間を増やせば、その分剰余価値も増殖するため、資本家は可能な限り労働時間を延長しようとする傾向にあります。
一日8時間の剰余価値+6,000円から、一日10時間にすれば剰余価値+10,000円になります。
ちなみに、技術革新など資本家による生産力の拡大によって生ずる利潤の増大を「特別剰余価値」、そういう生産力の拡大が社会全体の技術水準や生産力を引き上げることにより、労働力の再生産費が小さくなり、相対的に剰余価値が増大するのが「相対的剰余価値」です。
生産物からの疎外
非常に分かりやすくいえば、生産手段を労働者が持つ場合、その努力や頑張りによって得た「喰うに困らない程度(商品の再生産可能な程度)」以上の余剰分の成果は、全てそのまま自分のものになります。
これが資本家の持つ生産手段のもとで雇われの身として働く場合、その余剰分の成果は見えない形で剰余価値としてすべて資本家のものとなります。
生産手段を持つ自立した労働者のサイクルは「商品(生産物)→貨幣(売上)→商品(再度生産物を作るために必要なものの購入)→労働→商品(生産物)」となる訳ですが、資本家の強みはこの他人の労働サイクルそのものを商品に出来るというメタレベルの経済活動なのです。
「貨幣→労働力商品(労働者)→貨幣」の中で生ずる余剰分の成果はすべて資本家に抜き取られます。
しかし、この剰余価値というものは労働者の側からは基本的に見えません。
システムの単なる部品である私から全体を把握できず、資本家というシステム全体の価値配分を鳥瞰できる位置に立たなければ分からないからです。
あくまで私は生活のために自発的に契約を結んで、等価交換で自分の労働力を売っていると思い込んでいます。
資本主義というものがどんな過酷な奴隷社会よりもはるかに多くの搾取を可能とするのは、剰余労働を労働者側から自発的に生み出すことができるからです。
一般的なイメージとして、資本家はたくさん生産物を売ってたくさん儲けたいから(事業拡大)、その人手として多くの労働者を雇うと思われがちですが、裏を返せば、それは、たくさんの労働者を雇ってたくさんの剰余価値を奪取したいからこそ、たくさんの生産物を販売する必要があるとも言えるわけです。
「商品を売って儲ける」のは個人事業主の間だけであり、商売が多くの従業員を雇う規模になると儲けのパラダイムが「剰余価値(従業員)で儲ける」にシフトします。
機械などの設備投資によって生産性を上げても、投資額以上のリターンが得られるかどうかは分かりませんが(例えば、資金回収前に壊れたり、予想より利益率が低い)、無能であればいつでも解雇できる労働者は、資本家にとって絶対に負けることのない投資対象です。
そのため、消極的な資本家は人手不足が生じない限り、設備投資による生産性向上を目指さず、労働者からの搾取を優先します。
ロボットや無給で働く労働者(奴隷)なら最大の剰余価値が得られると考えてしまいますが、生産するのは”賃金労働者”である必要があります。
労働者は制服を脱げば、客になるからです。
もし、賃金労働者(客)が居なくなれば、市場が枯渇し、資本家も共倒れになります。
ですから資本家は、可能な限り安い賃金で、可能な限りよく働き、可能な限り高い値段で商品を買ってくれる労働者兼客を、可能な限り多く雇いたい(投資したい)のです。
人間(労働者)自体が最小の投資で最大の生産性(利益)を上げる投資対象になると同時に、その生産物(財・サービス)を自ら購入し資本家の利益を生むという、二重の搾取状態にあります。
絶えざる競争の中で
また、私は自分の労働力を繰り返し資本家に販売するということで生活を成り立たせています。
自分の販売商品である「自分の労働力」は、つねに「他人の労働力」という商品との競争にさらされているため、一定以上の品質の商品(労働力・がんばり)を提供しなければなりません。
こうして労働者は、自発的に隷属し、自発的に頑張って働くという構図が生み出されます。
だからといって資本家は奴隷をこき使って豪奢な生活を送りたいという目的だけで、剰余価値の増大を狙っているわけではありません。
資本家も労働者同様、他の資本家との激しい競争にさらされているため、価値増殖の追求や生産性の拡大を目指さなければ、資本家として生存競争に敗れてしまうからです(資本家はこの闘いで勝たねば自身だけでなく労働者の雇用も守れない)。
いわば資本家も労働者も競争に駆り立てられて、いやでも生産性を無際限に拡大していくのです。
とあるアクション映画にもあるように、それは加速することを止めればただちに爆発する列車のようなものです。
資本主義という機関はそういう危険なエンジンを内在することによってフル稼動しているという認識をもって、マルクスはその批判とするのです。
(以上は『資本論』という大著のほんのさわりの部分です。このエンジンは必然的にオーバーヒートして破裂するわけですが、それについてはまた時間がある時に書きます。)
おわり