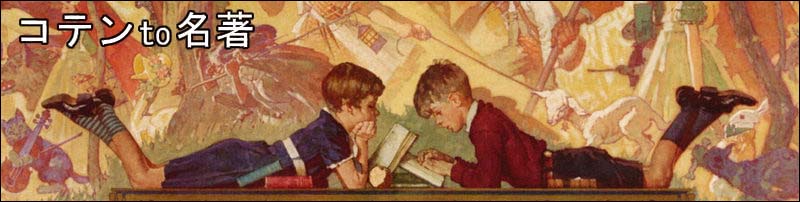わけの分からない現代美術
ここでいう現代美術とは美術史的な狭義のカテゴリーではなく、八百屋のおじさんが「現代美術はわけ分からん」と言う時の現代美術です。
リアルな描写や、美しい美人画や、光の印象が綺麗な風景画のように感性にうったえるものではなく、理屈っぽいアート、まさに「分かる分からない」といった理性的な範疇のアートのことです。
感じるものではなく分かるものという概念的(コンセプチュアル)なアートとしての現代美術について説明します。
美術館に入ると台の上に作品として便器がひとつ無造作に置いてある、「なんだこれ…」となるのが普通です。
画廊に入ると、空っぽの部屋に男性の気持ち悪いマスターベーションのあえぎ声がスピーカーから流れている、「バカかこいつは…」となるのが普通です(※1)。
しかしそんな訳の分からないものの中にも鑑賞者に伝えたい制作者の意図(コンセプト)があるはずです。
具体例1、京都人
日本の文化は非常にコンセプチュアルなので、分かりやすいようにそれを例としてあげてみます。
京都人は嫌なお客さんが来ても、笑顔で迎え入れお茶を振舞います。
その代わりに早く帰れのおまじないとしてほうきを逆さに立てかけるそうです。
実際にやっている人は稀でしょうが、それを知ったら「京都人、恐い」となります。
しかし、それは直接「帰れ」というような無粋なことは言わずに間接的に物事を表現する京都人の詩的な情緒とみなすこともできます。
他の地域から来た客人にとっては、「ほうきが立てかけてある、なんだこれ?」という感じでしょう。
これは先ほどの現代美術と同じ構図です。
無意味に見える立てかけられたほうきにもなにか意図(コンセプト)があるはずです。
もしかして「今は掃除の最中で忙しいんです、早く帰ってください」という意図かもしれません。
あるいは「ほうきは邪魔なものを掃きだす道具です、これであなたという邪魔ものを掃き出したいんです」という意図かもしれません。
美術鑑賞において正解などないわけで、そうやって自由にコンセプトをくみ取ればよいのです。
むしろ制作者の格好をつけた表面的なコンセプトよりも、鑑賞者の方が隠れた深い意図を読み取ることの方が多いでしょう。
重要なのはその意図をくもうという姿勢であって、「わけが分からん」の食わず嫌いで終わらせて自分の素直さを誇ることではありません。
具体例2、お坊さん
しかし、一見コンセプチュアルっぽくてもそうではなく、もっと高次のものを表現しようとするものもあります。
ただ、既存の絵画や彫刻や音楽や映像などの形式によっては表現できないものを感得させるためのものとして、わけの分からん表現手段をとる場合などです。
例えば昔、禅の坊主が弟子に既存の手段では伝えられない悟りの境地を感得させるために、いかにも現代美術的な装置を作って修行させました。
たくさんの鏡を集めて、内側に鏡面を向けた鏡の球体の部屋を作ります。
その中心に灯火をもった弟子を入れます。
鏡と鏡が映しあい、私が無限の私に囲まれた独特な空間の中で、しばらくすると自我の境界が崩れだし、自我からの解脱という悟りの境地を感得できるという仕組みです(※2)。
やはりここでも「わけが分からん」で終わらすのではなく、積極的に鑑賞してみることでしか分からないものが作品の中にあるわけです。
おわり
※1、ヴィト・アコンチの1972年の作品『シードベッド』のこと。下画像は画廊(ニューヨーク、ソナベンド・ギャラリー)の床に潜り込み、鑑賞者の女性の靴音を聞き自慰行為をし、自身の声を鑑賞者に聞かせるというパフォーマンスアート。サルトル的な見る-見られるの弁証法的関係、および実存的不安の表現です。やっていることは悟りの境地を鏡によって体感させようとした禅僧と同じです。

※2、誰が何時何処でやっていたか不明です。鈴木大拙全集(岩波書店)のどこかで挙げられていた事例で、勿論、デュシャン登場以前の話です。