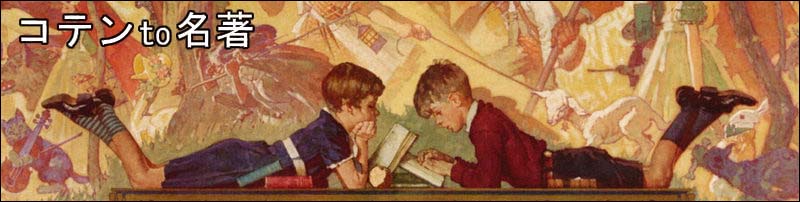第二章、現実(幻想)とどう関わるか
夢幻泡影の現実
つい80年前までの日本は、天皇陛下は神様でお国のために死ぬのが当然だった世界です。
現代でも飛行機で半日ほど飛べば、昔話に書かれた聖なる岩の争奪戦の為に国をあげての激しい戦争が行われています。
200年前の科学の教科書に書いていることが、ほとんど冗談のような内容であるように、200年後の未来の人々は現代の私たちの信じる科学的真実を笑い飛ばすでしょう。
そんな風に、ほんの少し鳥瞰的な視点で眺めただけで、人間が幻想の中で生きていることがよく分かります。
現代の日本で生きている私たちが現実だと思っている世界も、未来の人々や、離れた文化で生きる人々にとっては、幻想に過ぎないものと映るでしょう。
神様のように鳥瞰的な視点で見れば、いかなる人間の現実も束の間のエゴが生じさせる束の間の幻想だということに気付くはずです。
宇宙の塵にすらなれないようなちっぽけな私の主張が、過去の偉人や未来の賢人を差し置いて、正しい真実だなどと、いかなる権利や根拠をもって主張するのか、という話です。
幻想を隠蔽するための幻想
しかし、意識の高い一部の人間は、幻想から脱し現実と邂逅することが出来ると考えます。
映画『マトリックス』のように、利益とご都合で作られた安楽な虚構を脱し、醜く不条理で苦しいアンダーグラウンドな現実に目醒める、という構図です。
しかし、これは幻想を隠蔽するためのよりタチの悪い幻想にすぎず、アンダーグラウンドな現実そのものがより巧妙なマトリックス(虚構)であるという事に彼らは気付いていません。
(自称)現実主義者は、幻想に生きる世俗の凡人を見下し批判することで、自らは幻想の外にいるという錯覚を獲得し、自身は現実という苦役に耐え抜く選ばれし民であるという、クールでヒロイックな虚構の中で生きることができます。
現実感を得るためには苦しみが必要です。
例えば、夢の中で思いっきり頬をツネリ、痛ければ痛いほど現実である保証が得られる、というイメージを人はもっています。
これは、頭だけで作られた「夢」の中では、身体的な痛覚は無いだろうという素朴な推論(厳密にいうと夢の中でも痛覚は存在する)と、「幻想=易しく楽なもの、現実=厳しく苦しいもの」という先入観によって生じています。
例えば、プロレスは作り物のブック(虚構)であるがゆえに、リアルの総合格闘技以上に激しく当たり、血だるまになり、痛みや苦しみというリアリティーの徴(しるし)を与え、演者や観客が夢から覚めることを防ぎます。
利益や安楽や合理や調和から外れ、敢えて不利益や苦痛や不条理や混沌を自ら選ぶことによって、人はより自己の幻想(現実という名の幻想)を強化することが出来ます。
幻想を現実化するための徴
例えば、「戦争」は誇大で明白な幻想をもとに動きますが、痛み、苦しみ、不条理、混沌など、リアリティーの記号を沢山持っているため、「平和な日常が幻想であり戦争こそが人間のリアルなのだ」と反転して考えてしまいます。
実際は、平和な日常も戦争の非常も同じ程度に幻想です(幻想であることを積極的に隠蔽する戦争の方がタチが悪い)。
先に述べたように、幻想は自己の欲求や利益を充足させるという機能を有しているため、痛み、苦しみ、不条理、混沌など利益に反するものは、幻想に反するもの、つまり幻想の対義である「現実的なもの」という徴(記号学で言うコノテーション)になります。
例えば、宮崎アニメに出てくるような純真な子供の世界を描くものは幻想的で、子供のイジメや売春や虐待や家庭内暴力などをテーマにするどろどろしたドラマは現実的だと考えがちですが、どちらも同程度に現実的かつ幻想的です(統計的にはむしろ後者の方がより虚構に近いでしょう)。
後者の方が、幻想を現実化するための徴を沢山持っているというだけの話で、一種のモキュメンタリー(フェイクドキュメンタリー)的な詐術で現実と言う幻想(現実風幻想)を上手に見せているだけです。
幻想(現実)の機能、その一
生物であれ人間であれ、自己の欲求や利益のために現実世界を己の幻想で満たします。
それは、自己の欲求を充足するために便利な環境作りをしているとも言えます。
現実(という名の幻想)の第一の機能は、利益のための環境整備です。
問題は、現実(幻想)同士がバッティングするということです。
先述(一章六節)の変形フィルターは、a.生物的→b.人間的→c.文化(社会)的→d.個人的という順で、幻想がより可塑性を獲得し、複雑・曖昧になります。
つまり、a.とb.は安定的・共通的な幻想で争いは生じませんが、c.とd.においては多様化した幻想同士の争いが生じるということです。
社会の幻想vs個人の幻想
個人の幻想vs個人の幻想
社会の幻想vs社会の幻想
幻想同士の間で、利益相反することや、世界観的な矛盾が生じることも多く、幻想(自己の利益となる環境)作りが上手くいくとは限りません。
最悪、自身の現実(幻想)を守るために、個人間の殺し合い、文化間の戦争、社会に対する個人のテロ、個人に対する社会のテロ(粛清)に至ります。
ある意味、人間の争いの歴史は、幻想同士の対立です。
不利益な幻想という矛盾
この対立のゆえに、幻想の強要という事態が生じます。
先に述べた「戦争」のように、”自己の利益を阻害する幻想”などという矛盾した概念が生じる、一つの理由です。
社会あるいは支配者の欲求や利益を充足させるための幻想が、個々の成員に強要(特に洗脳的に)されることにより、”不利益な幻想”という矛盾が生じます。
幻想のために、本当は人を殺したくないのに殺し、死にたくないのに死にに行くのです。
自己の利益となるはずの幻想に、それと利益相反する他者の幻想が上書きされることで、このような矛盾が生じるのです。
それと同時に、苦痛や不条理などの現実の徴を無数に宿した不利益な幻想に、個人の有益な幻想が根負けして、「これが現実だ」と勘違いし、諦めて不利益な幻想を受け入れます。
安楽な平和=幻想、苦痛な戦争=現実という、ステレオタイプ化したイメージ「残酷な方がより現実だ」に流されず、どちらも同程度に幻想であり、むしろ不利益な幻想(現実という名の)は強要された幻想の可能性が高いという認知が必要です。
ちなみに、幻想が不利益な幻想となる第二の理由は、単純な錯誤です。
幻想が可塑性(いわば自由)を持つということは、誤りが生じやすくなるということです。
社会であれ個人であれ、よかれと思って為した環境整備(幻想作り)が悪い環境整備と成り、”不利益な幻想”という矛盾した概念が生じてしまうことになります。
三番目の理由は、先に述べた「現実の徴」として積極的に利用するためです。
後述する幻想の安定性という問題がある為、自己の現実(幻想)をずっと真の現実だと思い続けることは困難で、常に酔いから醒める危険に脅かされることになります。
子供と違い大人は、幻想を完全に幻想だと分かった興醒め状態のままでは、心を込めて人生を生きることができません。
幻想である『ドラクエ』をプレイするにも『ドラえもん』を読むにも、感情移入によって一時的にそれが幻想であることを忘れ、仮設的な現実に没入する必要があります。
ひと時だけでも童心に還り、幻想に没入する能力のない人(いわゆる醒めた大人)は、幻想を楽しむことが出来ず、『ドラクエ』はただのボタン押し事務作業になり、のび太が恐竜ピー助とお別れする感動シーンも、ただのインクの染みにしか見えません。
しかし、そんな醒めた人間でも、幻想に苦しみや混沌などと言う現実感の記号を混ぜることにより、幻想を疑似的に現実化することができます。
先に述べたマトリックスのマトリックスのように、既存の幻想を批判する幻想世界を構築することで、自分は幻想の外(つまり現実)にいるという錯覚を生じさせることができます。
こうして、不利益な幻想という矛盾したものが出来上がるのです。
多くの人々が、甘い夢から覚め、苦い大人の世界に入ることで、「幻想的な幻想」から「現実的な幻想(現実風幻想)」へと転向しますが、彼らは何ら変わることなく幻想の中で生きつづけています。
幻想(現実)の機能、その二
人間は幻想の無い状態(厳密には無ではなく瓦解状態、混沌)に耐えられません。
例えば、人間をいわゆるゲシュタルト崩壊的な混沌状態に晒すと、嘔吐したり失神したり発狂したりします。
人間は混沌を脱するためなら、藁でも、浅はかな幻想でも、何でもつかみ、とりあえず安定的な世界を構築しようとします。
得体のしれない激しい揺れ(地震のこと)の原因が”大ナマズの運動”でも”プレートの跳ね上がり”でもどちらでもよく、現実(幻想)を安定させ、混沌を回避させてくれるものなら、何でもいいのです。
現実(幻想)の第二の機能は、混沌を回避するための環境の安定化です。
例えば、人間は死(完全な無)を恐れると言いますが、実際は無になることを恐れているのではなく、自分が居無いことを想像できない堂々巡りの思考の混沌状態に強烈な不安を憶えているだけであり、自己の「無」を恐れている訳でも、まして無を認識している訳でもありません。
この不安(不安定)を無くし、安心(安定)を獲得するために、人は宗教的幻想などを利用し、死を想った時に生じる思考の眩暈を回避します。
幻想(現実)の安定性
例えば、「大ナマズの地震」と「プレート移動の地震」では、前者の方が幻想として脆く、それを現実(幻想)として採用した場合、すぐに壊されてしまう可能性があります。
原理的に物事を完全に実証することは不可能ですが、堅固さ(反証の困難さ)には差がある為、できるだけ堅固な幻想を選んだ方が安定します。
現代に生きる人であれば、新興宗教的世界観で現実(幻想)を構築するより、自然科学的世界観で構築した方が、長持ちし、個人の一生(数十年)くらいなら持ちこたえられる可能性が高く、幻想を現実だと思い違えたまま人生を終えることも可能です。
「大ナマズの地震」などと吹聴すれば周囲の人々にすぐに論駁され叩き潰されますが、プレートテクトニクス(地殻運動による地震)であれば、数十年はもつでしょう。
また、周囲に合わせ多数派の幻想に属した方が安定するため、特に少数派(マイノリティー)全般を見下し攻撃する傾向のある同調大国日本においては、多数派の自然科学的な世界観を採用した方が生き易いでしょう。
利益相反したり矛盾するような世界(幻想)を隣人が持っている場合、人は自己の幻想を護るために、攻撃することが多いので、できるだけ周囲とバッティングしないよう、ある程度己の幻想を調節する必要もあります。
例えば、宗教を馬鹿にする現代の日本では「神様」などと言うと袋叩きに合うので、「宇宙の摂理」などと自然科学的概念に偽装する宗教家はよくいます。
幻想(現実)の価値
現実(幻想)が、利益や欲求充足の為の環境整備(とその環境の安定化)であるとすると、幻想に良い・悪いという価値的な質が生じることになります。
良い幻想とは、当人の利益になることが第一条件で、第二にその利益が安定的持続的に確保できるものであることです。
安定的な幻想の為には、極力現実の確率が高い堅固なものを、多数派に属する保守的なものを、幻想を尊重し合う生産的姿勢を、選択する必要があります。
安定的持続的な利益の獲得のためには、他者や社会の利益(つまり他所の幻想)も同時に尊重する姿勢(商売で言う”三方よし”)が必須です。
例えば、カルト宗教的幻想は、本人に対し不利益になることも多く、幻想として脆く、少数派で、積極的に他人の幻想を壊しに行こうとするので、悪い幻想です。
サザエさん的な平和で平凡な幻想の中で生きている奥さんを喫茶店に呼び出し、「あなたの生きているのは偽の現実で、本当の現実は教祖○○様への帰依によって開かれます」などと洗脳し、良い幻想をもっている奥さんを悪い幻想に引きずり堕ろそうとします(つまり他者の幻想を尊重せず強要する)。
ですから、自然科学的幻想を信奉する者が新興宗教的幻想を信仰する者に対して、その幻想性と批判するべきではなく(そんな権利はない)、幻想として不利益であることを教示すべきでしょう。
現実(幻想)との付き合い方
現実(幻想)との付き合い方は、いくつかのパターンに分かれます。
・利益になる幻想を幻想であると気付かずに人生を終える、幸せな人。
・不利益になる幻想を幻想であると気付かずに人生を終える、不幸な人。
・幻想を脱した苦い現実に生きているという現実風幻想の中で生きる、半ば不幸な人。
・すべて幻想であることに気付き、幻想の陶酔の中で人生を楽しもうとする、幸せな人。
・すべて幻想であることに気付き、残りの人生を心のない事務作業として過ごす、不幸な人。
感動のみが現実
いかに現実世界が束の間の幻想であろうと、泣いたり、笑ったり、怒ったり、愛したり、心を動かす、直接的な感覚や感情そのものは現実です(第一章五節のデカルト的な現実性)。
作家のラビンドラナート・タゴールは、幻想のように変化していく世相よりも、変わることのない人間の基本的な感情を描きたい、と述べます。
たぶん、人間の人生の価値は、いかなる状況(幻想)に生きたかということよりも、いかに生きた(活きた)のかということにあるのでしょう。
状況が幻想だからと言って、このような人間の基本的(直接的)な現実まで失なってしまうのは、本末転倒です。
中世のキリスト教的幻想の中で神を愛し生きた人も、戦時中の天皇主義的幻想の中で祖国を愛し勇ましく散った人も、現代日本と言う幻想の中で誰かを愛し生きる私も、その愛の真摯さが似たものであれば、人生の価値も変わらず、皆、素晴らしいものであるでしょう。
多くの人は幻想の中身にばかりこだわり、その体験によって得られた直接的な感覚や感情の豊かさそのものは、おざなりにします。
たとえ億万長者の経営者や王様に成ったとしても、その幻想から得られた経験が、本人にとってただ苦しい恨むべきものでしかなかったとしたら、どうでしょうか?
たとえ貧しい音楽家や農夫として生きたとしても、その幻想から得られた経験が、本人にとって充実した素晴らしいものであったなら、良い人生であるとは思わないでしょうか?
いかなる幻想を選択するにせよ、一番重要なことは、その幻想の中で生きていてそれが感動(好い感情や好い感覚)を与えてくれるかどうかです。
これまでに述べた利益や欲求の充足は、生物学的な欲求の充足に留まらず、究極的にはこの感動と言う目的の為の手段ともなります。
良くも悪くも人間は、延命(物的豊かさ)を最大の目的とする動物と異なり、精神的豊かさを求める存在でもあります。
私たちは生きている限り永久にプレイヤーであるため、常に評価基準はプレイする自身の経験にあるはずです。
誰も他人の良い幻想を否定することは出来ず、また自己の幻想を真実と称し他人に強要する権利もありません。
社会や他人の圧力によって自分の望まない幻想を選択し、死んだように生きる人は、クラスメートの圧力によって強要された流行のゲームを、嫌々事務作業的にクリアする少年のようなものです。
少年は、何らかの感動の経験を得るために、ゲーム(幻想)をプレイする(楽しむ)のであり、そのゲーム内容が流行のものでなくとも、カッコ悪くとも、関係ありません。
世間の言う「クソゲー(クソみたいな幻想)」であったとしても、プレイヤーがそれを感動し楽しめるなら、あくまで名作ゲーム(素晴らしい人生)です。
幻想の力
幻想と現実の相克に悩むことが出来るのは、ごくごく限られた生物のうちの限られた個体のみです。
パスカルが広大な宇宙を眺め、ほとんど無に等しい存在である人間の虚しさを感じながらも、「だからこそ」人間は稀有で偉大であるという積極的な転回をみせたように、人は泡沫夢幻の現実に気付いた時、「だからこそ」人生は素晴らしいと言えるはずです。
それは「人生は泡のように儚いから尊い、美しい、面白い」とか言うようなセンチメンタルな諦めや怨嗟(ルサンチマン)を含んだ逆説(価値転倒)ではなく、人間にとって幻想が自己の存在条件そのものであると自覚し、転回し(いわゆるパラダイムの変更)、それを当たり前のものとして積極的に扱うことです。
「ごっこ遊び」という幻想を全力で楽しむ子供の姿が、人間にとって自然であり、幻想を卑下する現実という名の幻想を「現実」だと自己欺瞞的に自分に言い聞かせる大人は、むしろ転倒的な不自然な存在であると言えるでしょう。
社会の成員が個人の幻想を捨て、現実という名の社会的共同幻想に参入することで、社会は維持・繁栄するため、私は大人になるにつれ、おのれ独自の幻想を捨て、現実という名の幻想に馴化していきます。
現実(社会的共同幻想)は、私が本当に感動する個人的幻想を差別的に見下し、幼稚で劣った捨てるべきものであると恫喝し、適不適・好き嫌い問わず、すべての人々をたった一つのゲーム(社会的共同幻想)に強制的かつ矯正的に参加させようとします。
「幻想(個人的幻想)は悪いもので、現実(社会的共同幻想)は善いものである」と洗脳され、私は自ら幻想(個人的幻想)を楽しみ感動することを禁忌し、たった一つの幻想(社会的共同幻想)を嫌々、事務作業的にプレイすることを余儀なくされるのです(運よくそのゲームに適合した人を除き)。
現実は己が幻想であるという事を巧妙に隠すことによって特権的な地位を得、他の幻想を蹴散らし、絶対的な支配者となることができます。
しかし、一部の賢人は彼(現実)が裸の王様であることを暴露しますし、歴史に学ぶ者はその鳥瞰的な視点によって現実の相対性を理解しますし、一般人であっても現実のタガが外れる喪失経験などによって、一時的にでも現実の幻想性を垣間見ます。
セブンイレブンの歌で有名な『デイ・ドリーム・ビリーバー(白昼夢を信じる人)』の歌詞(忌野清志郎版)のように、大切なものの喪失経験の後には、多くの場合、現実の幻想性が一時的に露わになり、私たちが現実だと思っていることが白昼夢にすぎないのではないかという疑問が生じます。
いかに現実(幻想であることを忘却あるいは隠蔽した幻想)が安定的なものであったとしても、幸か不幸かその幻想性に気付いてしまう人も多く居り、その際、ある種の不安や恐怖を感じることになります。
上述のように、私たちは幻想を楽しむという力を剥奪されているがゆえに、現実が幻想であると知った時、恐怖を覚えてしまうのです。
もし、私が、もはや手遅れで、幻想を楽しむ力を完全に失ってしまっているなら、現実が幻想であるという事の認知は、ある種のニヒリズムを意味し、残りの人生は心のない事務作業と化すでしょう。
もし、私が、子供の頃に持っていた幻想を全力で楽しむ力を、もう一度取り戻すなら、幻想は積極的なものとして機能しはじめるでしょう。
三島由紀夫は芸術家の条件として「真水で酔うこと」の重要性を述べましたが、その芸術的能力を子供の頃には皆、持っていたはずなのです。
現実に馴化し上手くその社会的共同幻想を楽しめるなら、デイドリームビリーバーのままで居れば良いのですが、現実が退屈で苦しいものであるなら、もう一度、その力を取り戻し、子供のように主体的に世界(幻想)を楽しむことが必要になるかもしれません。
寛容な心
人間が己の幻想を真の現実だと考え、他の幻想に対し不寛容である限り、争いは永久に止むことがありません。
グリフィス監督の映画『イントレランス(不寛容)』では、古代から現在までの歴史の各時点における幻想同士の激しい闘争をクロスカッティングで同時並行的に描き、人類の悪しき本質としての「不寛容」を抽出しました。
私は私の所有する現実が幻想にすぎないと知った時、はじめて他者の幻想に対しても寛容になれます。
不完全な存在である人間には、全能の神のような、現実や真実を断定する力も権利もありません。
私たちが争うべき「現実」とは、「混沌とした事物に安定的な調和をもたらす合理的な説明(世界像)を与え、かつ、人間にとって可能な限り利益(幸福)となる、社会的共同幻想」のことです。
先に述べた、映画『マトリックス』の仮想現実「MATRIX(母体、基盤の意)」は、外部の者に強制的に与えられたものであり、それは独裁国家の成員に洗脳的に与えられる社会的共同幻想(現実)の在り方に似ています。
しかし、社会的共同幻想は、独裁的な在り方ではなく、民主的な在り方においても作ることが出来ます。
内部の者が主体的に協力・議論しながら、マトリックス(社会的共同幻想)を自ら作ることです。
自分の見る夢を自分で描くという、メビウスの輪のような構造で、奇妙に聞こえるかもしれませんが、私たちは普段から問題なくこのような作業をしています(気付かぬまま、あるいは気付かないふりをして)。
表と裏がひっくり返る捩じれた部分(表裏が合一的に変換する部分)を自己欺瞞的に隠すことで、「現実(表)」と「虚構(裏)」の同一性を隠蔽し、対立するものに仕立て上げ、差別的に幻想を現実に成れない従属的(不完全)なものとして見下し、現実の優位性を主張しているだけです。
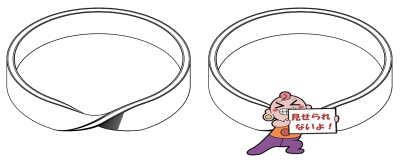
人間が争う時、どちらが真の現実かを問題にするべきではなく(そんなことは決定不可能)、どちらがその時代その場所においての幻想として質(安定性・利益性)が高いかを競うべきだということです。
また、そのような自覚(己が幻想であること)と他者との協力によって獲得された社会的共同幻想であれば、その世界観に対立するような個人や他の社会集団の幻想に対しても、ある程度寛容になれるはずです。
その人自身、あるいはその共同体自体が幸せであり、他者にあまり迷惑をかけない幻想であれば、自由にさせておけばよい、という事になります。
自己の幻想を真の現実だと思えば、その世界観に反する幻想は存在するだけで自己の否定となるため、不寛容とならざるを得ませんが、自身も他者も質が違うだけの同類(同じく幻想)であると認識するなら、積極的に害を加えてくるような幻想でない限り受容できるでしょう。
おわり