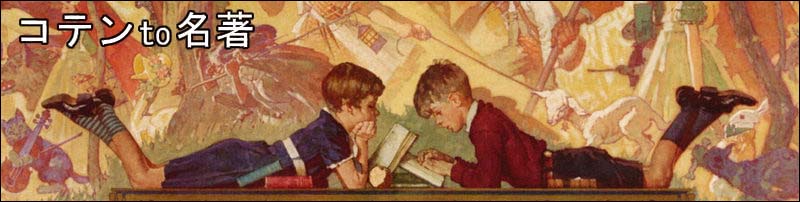はじめに
世間一般で哲学者とカテゴライズされる人は、いくつかのタイプに分かれます。
本物の哲学者とは、一体どのタイプでしょうか。
一、謎解き制作者としての哲学者
『ドラゴンボール』という人気格闘マンガの中で「超聖水」というアイテムが登場します。
飲むだけで己の力が何倍にもなる格闘家憧れの仙人秘伝の聖水です。
しかし、実は中身はただの水道水であり、高い塔の頂上にあるその水を手に入れるために雲の上まで登るという困難な行程そのものが修行となり、強くなったと勘違いする仕組みです。

難解な哲学書も、多くがそれに似たものです。
おばあちゃんの知恵袋以下の当たり前のこと(いわば水道水)を、難解な用語と修辞と論理構成で語り、ある種の困難な謎解きを作ります。
読者はその困難な謎解きの道を修業のようにめぐり、最終的にその「当たり前のこと」を理解した時、さもものすごい真理を手に入れたかのように錯覚します。
支払った努力がその物の価値を決定するという心理的効果と同時に、アクセスの困難な場所にある情報には高い価値があるという先入観によって、水道水は聖なる水として扱われます。
その手の哲学者は、浅い水たまりを掻きまわし底なしの深淵に見せることで、まるで自身が深い真理を有する人間のように権威付けます。
そして、衒学的な物言いに憧れる思春期の人々は、見事にそれに引っかかってしまいます。
カントの『純粋理性批判』のような必然的な難解さ(中身の濃いことを言っているから難しい)であれば問題ありませんが、多くの場合、中身が薄いことを誤魔化す為の不必要な難解さです。
二、仲介者(注解者)としての哲学者
日本で哲学者と呼ばれる人の大半がこれに当たります。
一般人や学生には読むことの難しい(内容的にも形式的にも)古典的名著や現代思想を、仲介(注解)的に伝達してくれる人々です。
実質は、ただの教育者のポジションなのですが、哲学の先生ではなくなぜか哲学者とカテゴライズされます(どの分野でもプロプレイヤーの大半が実質はコーチ業で食っているプロコーチですが、そういう意味で言っているのではなく、日本の哲学においては新しいものが生じないため仲介業化している、という話です)。
一見、独創的あるいは新しい思想を語っている哲学者に見えても、それは過去や海外の賢人の思想の装飾を替えただけのものか、複数の模倣のキマイラのようなもので、本質的には仲介者です。
仲介者から一歩進んで、そのような膨大な智恵のストックから、同時代的問題を解決するための処方箋を出すことに注力する人もいます。
三、素人としての哲学者
他人の考えに依拠する先の仲介者とは逆に、全く他人に頼ろうとせず、とにかく自分の頭で考えようとする人々がいます。
先行研究を参考にしないので、せっかくのアイデアが無駄に終わることの方が多いですが、バイタリティーのある人が多く、数を打つので当たります。
例えば、発明家のバックミンスター・フラーはこのタイプの人で、彼のアイデアに対し、「そんなことは既に過去の偉人が発見している」と専門家たちに嘲笑を向けられることがよくありました。
そんな時、フラーは、偉人と同じ考えに独力でたどり着いたことを喜んでいました。
↓ジョン・レノンの次のワイヤードームを持ったおじさんがフラー
四、ほんまもんとしての哲学者
過去の学問を完全に学び終えた後に、「書」を捨て(つまり他人の思考に依存することを止め)自分の頭で世界を読み解こうとしたデカルトが、哲学者のひとつの理想像です。
仲介哲学者(他人に学ぶ人)と素人哲学者(自分の頭で考える人)の両方の良さを総合した、本物の哲学者です。
書(いわばアカデミズム)には権威と富を生じさせる力があるため、それを捨てるには相当の勇気や自信や経済力などが必要です。
五、根源を追究する者としての哲学者
万学の祖であるアリストテレスは、万学そのものを奴隷の学問であると考えます。
物理学や医学や政治学などあらゆる専門の学問は、人間の利益を目的とした実践的な学問にすぎないからです。
それに対し、「存在とは何か」というような、何の利益にもならないような根源的な問いを探究するのが哲学(形而上学)であり、これこそが王者の学問です。
利益になることを探究するのは実利的欲求の満たされていない奴隷、利益にならないことを探究するのは実利的欲求の満たされた王様、という訳です。
根源的な問いであればあるほど普遍化するため、具体と専門を必要とする実践には役立ちません。
数学の難しい計算は多くの利益をもたらしますが、「数とは何か」という根源的な探究は、誰の利益にもなりません(その学問が危機的状態にあり、根源からの革新を必要とする場合は別)。
ですから、根源的な問い、原理的な問いを探究する人は哲学者と言えます。
己の市場価値を上げるための資格の勉強(奴隷の学問)をしている時、ふと「何のために私は生きているんだろうか」という何の利益にもならない根源的な問い(王者の学問)が生じ、思いに耽ることがあります。
その時、私は哲学者(根源を追究する者としての)なのです。
六、知を愛する者としての哲学者
哲学の語源は「フィロソフィア」であり、日本語で「知を愛する」です。
訳語の「哲学」は、「希哲学」の省略されたものであり、「哲(賢明、知恵ある)」を「希(こいねがう)」という意味です。
素直に「愛知学」と訳した方が良いのですが、日本の哲学者は衒学趣味(カッコつけ)が多いので仕方ありません。
ソクラテスの言う「知を愛する」とはどういうことかと言うと、第一に、愛する人のように「知」を一番大切にせよ、ということです。
第二に、無知を常に自覚し続け、知への愛を維持しろ、ということです。
私たち人間は、選ばれし万物の霊長(理性的存在)と偉そうに自負しながら、まったく「知」を大切にしません。
金の為に、出世の為に、虚栄心の為に、性的快楽の為に、身の安全の為に、そのような様々な私利私欲の為に、平気で「知」を見捨て、間違ったことを正しいことだと言い張ります。
ソクラテスは法廷で処刑をチラつかせられても、堂々と真理を述べ、殺されました。
彼は、自分の命よりも「知」を愛していたからです。
それに対し、ガリレオは刑罰を恐れ、自分が生涯をかけ発見した真理を見捨てました(ガリレオ裁判)。
ガリレオは「知」よりも、自分の方を愛していたからです。
現代でも、命を懸けて真理を訴え、権力者に殺されてしまう人々が多くいます。
そんな人々こそ「哲学者(知を愛する人)」なのです。
それは知識の量ではなく、生き方の問題です。
私たちは利益のために、日々、「知」を見殺しにしています。
出世のために上司の嘘を真実だと受け容れ、仲間外れを恐れて間違ったことに同調し、常に利益になる方の選択を真実だと自己欺瞞的に言い聞かせ、行動しています。
知を愛する人(哲学者)であれば、金より地位より女より安楽より真理を選び、貧しさや孤独や労苦や死など決して恐れません。
恋人が居ない(満たされない状態)からこそ、異性を愛し求めるように、人は無知を自覚するからこそ、知を愛し求めます。
自分が賢い(有知)と思った瞬間、知への愛は失われ、自分は無知だと思った瞬間、知への愛の情熱が湧き起こります。
子供の頃は、皆、好奇心いっぱいで、何にでも問いを向け、知への求愛が止みません。
しかし、大人になるにつれ、知への情熱は薄れ、分かった風を装い、老年になる頃には悟りを開いた者のような無心(というか無関心)の境地に至ります。
世界は無限の謎(問い)に溢れているため、子供が大人になったところで知識の量に大差はありません(宇宙の広大さに比べればクジラとイワシの大きさの差など無いに等しい)。
老人は知識を得て悟りを開いたのではなく、慢心(自分は有知者であるという勘違い)や老化によって、知への好奇心や情熱(つまり求愛)を失っただけなのです。
それに対し、哲学者(愛知者)は、世界の広さ(無限の問い)と己の小ささ(無知さ)を自覚する謙虚さを持ち続け、死ぬまで知を愛し求め続ける者です。
おわりに
人間の定義(本質)をいかなるものと考えるかは、人それぞれです。
知性が無ければ人間でない(ホモサピエンス)、愛が無ければ人間でない(ホモアマンス)、遊びが無ければ人間でない(ホモルーデンス)などというように、定義付けはその人の生き方そのものに関わってきます。
哲学者の定義(本質)は、多分、一の衒学的謎解き制作の上手い人や、二の仲介者ではないはずです。
三・四の自分の頭で考える人、五の根源的なことを考える人、六の知を最も大切にする人、無知を自覚し続ける人などが、哲学者の本質的な特徴でしょう。
これはアカデミックな専門学者(常に他人の思考-流行の学説-に依存し、根源的なことは面倒なので無視し、知を私利私欲のための道具として利用し、自分の知識をひけらかし威張る)とは正反対の特徴です。
ソクラテスやキリストが乞食同然であったように、真理は世俗的な利益とは非常に相性が悪く、哲学者として生きるということは、いばらの道であるという事です。
人間の社会は、嘘や間違いや不正を分かった上で、それが真で正であると欺瞞的に受容すること(いわゆる大人の事情を汲む)によって成り立っています。
真理は、そういう社会的なれあい(共同幻想)を破壊してしまうものである為、真理を求める愛知者がただで済むわけがありません。
ただ、知を愛する者は、愛するものの為なら自分の財産や命など惜しくはないので、いかなる妨害も攻撃も効きません(希望的観測)。
おわり